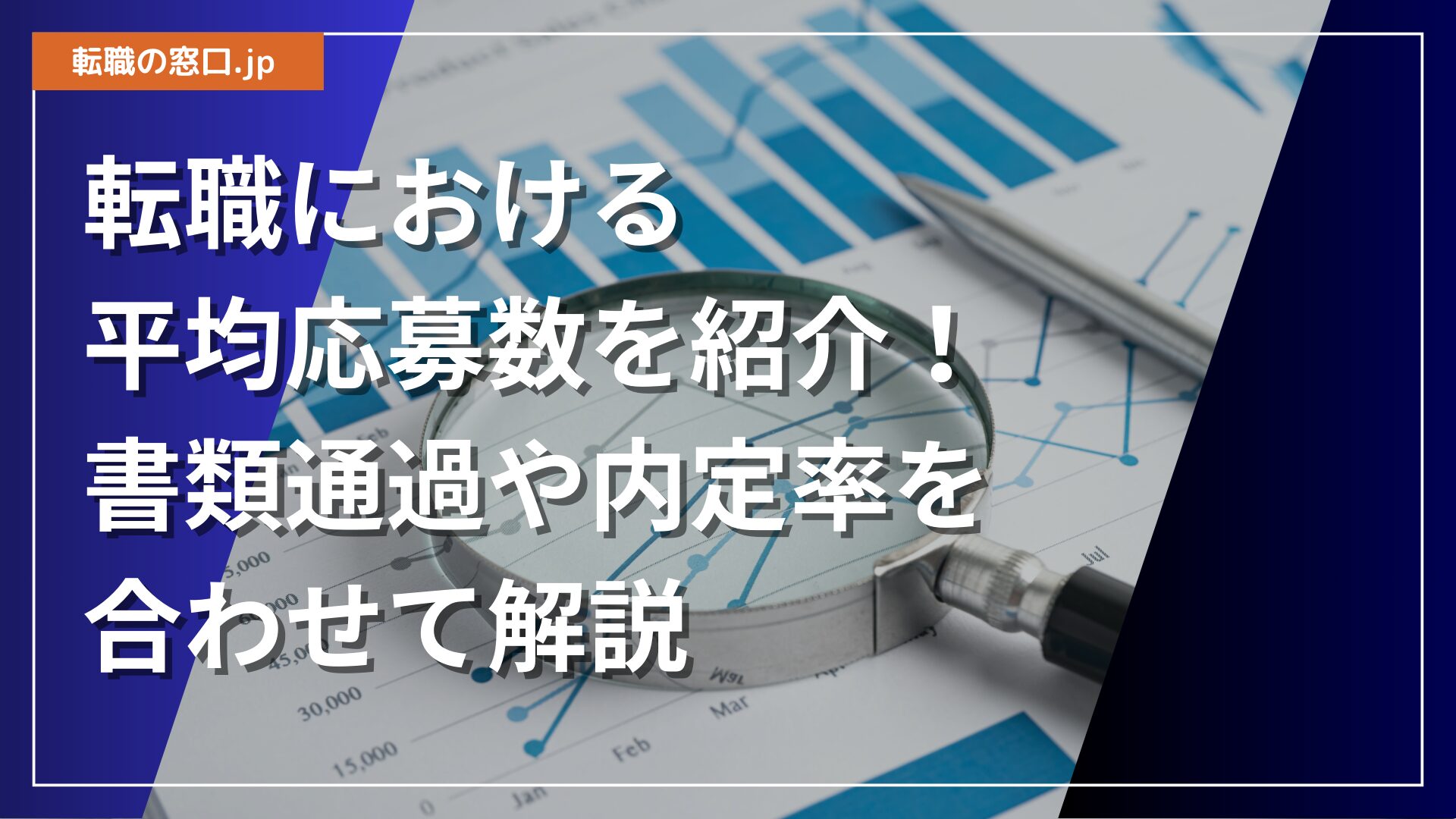転職活動をする際、「応募する企業は厳選したほうがいいのか?」「何社くらい応募するのが普通なのか?」と疑問に思う人は多いでしょう。1社だけに絞って挑むのも一つの方法ですが、実際の転職成功者の多くは複数の企業に応募しているのが実態です。
では、転職を成功させた人は平均して何社に応募しているのでしょうか?また、自分と似たキャリアの人はどれくらいの応募数で内定を獲得しているのでしょうか?
本記事では、転職活動における平均応募数を紹介し、書類通過率や内定率についても詳しく解説していきます。
転職での平均応募社数

転職活動では、どれくらいの企業に応募するのが一般的なのか気になる方も多いでしょう。実際のデータによると、転職希望者が平均して応募する企業の数は約8.4社となっています。
詳細に見ると、年齢が上がるにつれて応募社数が増加する傾向が見られます。これは、経験を積んだ人ほど希望条件が明確になり、多くの企業を比較しながら最適な選択をしようとするためです。一方で、20代の転職者は比較的少ない応募数で転職を決めるケースもあります。
つまり、転職活動における応募数の平均は8.4社ですが、年齢やキャリアによって異なるため、自分の状況に合わせた戦略を立てることが重要です。
| 年齢 | 応募数 |
|---|---|
| 〜19歳 | 4.1社 |
| 20〜25歳 | 6.3社 |
| 26〜30歳 | 7.1社 |
| 31〜35歳 | 8.2社 |
| 36〜40歳 | 8.7社 |
| 41〜45歳 | 10.1社 |
| 46〜50歳 | 12.1社 |
| 51〜55歳 | 14.5社 |
| 56〜60歳 | 14.5社 |
| 61歳以上 | 15.2社 |
参照元:マイナビ転職(【転職活動、何社応募した?】平均応募社数や、選考通過・内定の確率はどれくらい?)
転職における書類通過率と面接通過率

転職活動では、応募した企業の選考をどれくらいの確率で通過できるのかを把握することが大切です。特に書類選考や面接の通過率を知ることで、必要な応募数の目安を立てやすくなります。
ここでは、転職市場における書類通過率・面接通過率の平均について詳しく解説します。
転職活動期間はどれくらいかかる?流れや長引かせないポイントを解説
■ 書類通過率は平均30〜50%
■ 面接通過率は書類選考通過者の約50%
■ 転職で内定を得るために必要な応募数の目安
書類通過率は平均30〜50%
転職を成功させるために重要なのは、書類選考をどれだけ突破できるかです。一般的に、転職市場における書類通過率は30〜50%とされています。
例えば、100人が応募した場合、30〜50人が書類選考を通過し、次の面接へと進むことになります。人材紹介サービスを利用した場合、求職者1人あたりの応募社数が20社を超えることもあり、応募数の多さによって通過率が変動することもあります。
また、経験者を優先する求人では、未経験者にとって書類通過のハードルが高くなる傾向があります。転職成功の確率を高めるには、応募書類の質を上げることが不可欠です。
【例文付き】転職の履歴書作成で使える自己PRの書き方とコツを紹介
面接通過率は書類選考通過者の約50%
書類選考を通過した後、面接で内定を獲得できる確率は約50%といわれています。
マイナビのデータによると、面接に進んだ3.5件に対し、内定獲得数は1.6件と報告されており、この数値からも妥当な通過率であることがわかります。仮に4社の面接を受けた場合、平均的には約2社から内定を得られる計算になります。
ただし、面接の回数や企業の選考基準によって実際の通過率は異なるため、複数の企業に応募することが転職成功のカギとなるでしょう。
転職の最終面接で使える逆質問10選!社長や役員への効果的な質問例
転職で内定を得るために必要な応募数の目安
これらのデータをもとに考えると、転職活動では最低でも6〜10社に応募するのが一般的な目安といえます。ただし、業界や職種、個人のスキルや経験によって選考通過率は異なるため、一概に決めつけることはできません。
さらに、企業によっては筆記試験や複数回の面接を課すことがあり、内定を得るまでのプロセスが長くなるケースもあります。
第一志望の企業から内定をもらえるとは限らないため、できるだけ多くの企業に応募し、選択肢を広げておくことが重要です。
転職活動で複数の企業に応募する3つのメリット

転職活動では、複数の企業に応募することで成功率を高められます。特に、内定獲得の可能性を広げ、条件を比較しながら最適な転職先を選べるだけでなく、1社ごとの結果を待つリスクを回避できる点は大きなメリットです。
ここでは、転職における応募数の平均を踏まえながら、複数応募の重要性について詳しく解説します。
1. 内定獲得の可能性を高める
2. 条件を比較しながら転職先を選べる
3. 1社ごとの結果を待つリスクを回避できる
1. 内定獲得の可能性を高める
転職で内定を得るためには、1社のみではなく複数の企業に応募することが重要です。その理由は、応募数を増やすことで選考通過のチャンスが広がり、結果的に内定を獲得できる確率が高まるからです。
実際、1社だけに応募し、その選考に落ちてしまった場合、最初からやり直す必要がありますが、複数応募していれば「まだ次がある」と前向きな気持ちを維持しやすくなります。
例えば、書類通過率が平均30〜50%とされる転職市場では、10社に応募すれば3〜5社の書類選考を突破できる計算になります。選考の機会を増やすことで、転職活動の成功率を上げることができるのです。
そのため、納得のいく転職を実現するためには、気になる求人に積極的に応募することが重要です。
2. 条件を比較しながら転職先を選べる
複数の企業に応募することで、より良い転職先を選択しやすくなります。求人情報だけでは企業の実際の雰囲気や働き方は分かりにくいものですが、選考を進めることで、より詳細な情報を得られるからです。
例えば、面接を通じて会社の社風や評価制度、働き方について深く知る機会が増え、「思っていたよりも自分に合う職場だった」と気づくこともあります。
さらに、自分では意識していなかったスキルや経験が企業から高く評価されることもあり、キャリアの選択肢を広げるきっかけにもなります。
複数の企業と接点を持つことで、より理想的な転職を実現しやすくなるでしょう。
3. 1社ごとの結果を待つリスクを回避できる
1社の選考結果に依存することは、転職活動におけるリスクを高める要因になります。もし不採用になった場合、また一から企業探しをしなければならず、転職期間が長引く可能性があるためです。
一方で、複数の企業に応募していれば、1社が不採用でもすぐに次のチャンスに進むことができ、スムーズに転職活動を続けられます。
例えば、複数の選考を同時進行させることで、1社目の面接を通じて得たフィードバックを次の企業の面接に活かすことも可能です。
また、最終的に内定を複数獲得できれば、その中から最も希望に合う企業を選ぶことができるため、より納得のいく転職が実現しやすくなります。
転職活動の複数応募における注意点

転職活動において、複数の企業へ応募することは一般的であり、内定獲得の確率を高める効果があります。
しかし、応募数を増やすことで発生する課題もあり、スケジュール管理や情報整理が必要になる点には注意が必要です。ここでは、複数応募の際に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。
■ 面接日程の調整が難しくなる
■ 準備ができず片手間になる
■ 応募先企業の情報整理が大変
面接日程の調整が難しくなる
複数の企業に応募すると、面接日程の調整が負担になる可能性があります。特に在職中の場合、仕事と並行しながら選考を進めることになるため、スケジュール管理を徹底しなければなりません。
例えば、面接の日程が重なってしまうと、いずれかの企業の調整を依頼する必要が出てきますが、頻繁な日程変更は応募先に悪い印象を与えかねません。
そのため、応募する際には、エクセルやスケジュール管理アプリを活用し、各企業の応募日や選考ステップを整理しておくことが重要です。複数応募を成功させるためには、事前の計画と調整力が欠かせません。
準備ができず片手間になる
応募数が増えると、それぞれの企業に十分な準備をする時間が限られるため、1社ごとの対策が手薄になってしまうリスクがあります。転職活動では、企業研究や履歴書・職務経歴書の作成、面接対策など、入念な準備が必要です。
例えば、志望動機を企業ごとにカスタマイズせずに使い回してしまうと、採用担当者に熱意が伝わらず、選考で不利になる可能性があります。
そこで、応募する企業の優先順位を明確にし、「年収○○万円以上」「勤務地が○○エリア」など、自分にとって譲れない条件を設定することが大切です。
効率よく転職活動を進めるためにも、戦略的に応募先を選びましょう。
【テンプレート付】転職回数10回以上ある人に向けた職務経歴書の書き方
応募先企業の情報整理が大変
応募数が増えるほど、各企業の情報を管理する手間も増します。企業の特徴や選考状況を整理せずに進めると、混乱してしまい、志望動機や選考フェーズを取り違えてしまうこともあります。
例えば、面接時に他社の条件や業務内容と混同してしまうと、企業への理解が浅いと判断され、評価が下がる可能性があります。
そのため、応募前に企業ごとの情報をノートやデジタルツールにまとめ、自分のスキルやキャリアプランと照らし合わせながら応募する企業を選ぶことが重要です。
応募数を増やせば内定率が高まるとは限らず、むしろ準備不足によってチャンスを逃すリスクがあることを理解しておきましょう。
転職が決まらない人が持つ7つの共通点と不安の解消ができる対応策を解説
転職が難しいと感じる人が持つ3つの特徴と成功させるコツを紹介
転職活動でそれぞれの応募戦略の特徴

転職活動では、自分に合った応募戦略を選ぶことが成功の鍵となります。応募数を増やすことで多くの企業を比較でき、選択肢が広がります。
一方で、応募先を絞ることで、企業研究や選考準備に時間をかけられるメリットがあります。
ここでは、多くの企業に応募すべき人と、応募数を絞ったほうがよい人の特徴について解説します。
■ 多くの企業に応募すべき人の特徴
■ 応募数を絞ったほうがよい人の特徴
多くの企業に応募すべき人の特徴
転職活動で多くの企業に応募するべきなのは、できるだけ多くの選択肢から比較検討したい人や、新しい業種・職種に挑戦する人です。応募数が増えれば、より自分に合った企業を見つける可能性が高まります。
特に未経験業種に挑戦する場合、中途採用では即戦力が求められるため、書類選考の通過率が低くなりがちです。
例えば、広告営業の経験を活かして消費者向けの商品提案を行いたい場合、食品メーカーや保険業界の営業職に複数応募することで、自分のスキルを活かせる企業を見つけやすくなります。また、未経験歓迎の求人は若手を対象とする傾向があるため、30代中盤以降の人はより多くの企業に応募する必要があるでしょう。
さらに、転職活動を短期間で終わらせたい場合も、並行して複数の企業に応募することで、1社ずつ進めるよりも短期間で内定を獲得できる可能性が高まります。転職活動が長引くと、離職中の人は収入面の負担が増え、在職中の人も時間の確保が難しくなるため、スピーディーに進めたい人にはこの方法が適しています。
加えて、転職に失敗するリスクを抑えたい人も、応募数を増やすべきです。統計的に、1件の内定を得るには平均で10社程度の応募が必要とされています。応募数が少ないと内定を獲得できなかった場合に再び転職活動をやり直すリスクが高くなるため、慎重に進めるなら複数応募がおすすめです。
【2025年版】転職でおすすめな職種と業界10選!未経験でも挑戦可能な業界とは
異業種への転職は約5割!?転職者の動向とおすすめエージェントを紹介
応募数を絞ったほうがよい人の特徴
転職活動において応募数を絞るべきなのは、転職条件に強いこだわりがある人や、同業種・同業界での転職を考えている人です。応募先を絞ることで、企業研究や書類作成に時間をかけられ、より質の高い応募が可能になります。
例えば、年収や勤務地、職種などの条件にこだわりがある場合、多くの企業に応募すると条件がブレてしまい、結果的に納得のいく転職ができない可能性があります。事前に優先順位を明確にし、条件を満たす企業を厳選することが大切です。
また、同業界・同業種での転職を希望する場合、業界の知識や経験を活かせるため、特定の企業に集中して応募することで、企業とのマッチング精度を高められます。
さらに、転職活動にかける時間が限られている人も、応募先を絞るべきです。多くの企業に応募すると、企業研究や面接準備に時間がかかり、本業や生活との両立が難しくなる可能性があります。
特に在職中の転職活動では、無理に応募数を増やすよりも、選考を突破できる可能性が高い企業に絞る方が効率的です。時間がない場合は、転職エージェントを活用し、自分に合った企業を効率的に見つけるのもよいでしょう。
おなたに会う転職サービスが見つかる
転職を成功させるためには、自分に合った転職サービスを活用することが重要です。特に、応募数を増やしながら効率よく転職活動を進めたい場合、転職エージェントの利用が効果的です。
転職エージェントを利用すると、キャリアアドバイザーが希望条件に合う求人を提案してくれるため、自分で企業を探す手間を省くことができます。さらに、応募書類の添削や面接対策、内定獲得後のサポートまで一貫して受けられるため、在職中でもスムーズに転職活動を進められるでしょう。
例えば、公開求人数の多さやサポートの充実度を基準に、人気の転職エージェントを比較した記事もあります。転職活動にかけられる時間が限られている人は、こうしたサービスを活用することで、より短期間で理想の転職を実現しやすくなります。
応募数の平均を意識しつつ、効率よく転職活動を進めるために、ぜひ自分に合った転職サービスを見つけてみてください。
【2025年最新】転職エージェントおすすめ30選!成功に導くエージェントの選び方も紹介
【2025年最新版】転職サイトおすすめランキング43選を分野別に徹底比較
【2025年最新版】女性におすすめな転職サイト比較ランキング20選
転職の応募数に関するよくある質問【Q&A】

転職活動を進める際、「何社応募すべきか」「応募しすぎた場合の対策」など、応募数に関する疑問を持つ方は多いでしょう。
ここでは、特に多く寄せられる質問に対し、具体的なアドバイスを紹介します。
Q1. 転職活動で100社応募は多すぎる?
Q2. 応募しすぎて選考を管理できない場合の対策は?
Q3. 応募した企業を辞退する際のマナーは?
Q4. 30代・40代は何社くらい応募すべき?
Q1. 転職活動で100社応募は多すぎる?
100社への応募は、多すぎるかどうかは人それぞれですが、現実的には10社程度が適切といえます。なぜなら、応募数が増えるほど一社ごとの対策が疎かになり、結果として選考通過率が下がる可能性があるからです。
例えば、企業ごとに異なる志望動機を作成し、適切な面接準備を行うには相応の時間と労力が必要です。
特に働きながらの転職活動では、複数社を同時進行するのは容易ではありません。そのため、選考準備に支障が出ない範囲で応募数を調整し、質の高い対策を行うことが大切です。
Q2. 応募しすぎて選考を管理できない場合の対策は?
選考管理が難しくなった場合は、状況に応じて応募数を調整することが重要です。理由は、転職活動は計画どおりに進むとは限らず、進捗に応じた柔軟な対応が求められるからです。
例えば、初期応募した数社で選考が進んでいるなら、新規応募を控え、面接対策に集中するのが賢明です。
一方で、なかなか書類通過しない場合は、応募数を増やしてチャンスを広げるのも有効な戦略です。応募と選考のバランスを見極めながら、効率的に転職活動を進めましょう。
Q3. 応募した企業を辞退する際のマナーは?
応募後に辞退を決めたら、すぐに連絡することが社会人としてのマナーです。なぜなら、企業側は求職者の対応をもとにスケジュールを調整しているため、連絡が遅れると企業に迷惑をかける可能性があるからです。
例えば、面接の日程調整後に辞退を伝える場合、1日遅れるだけでも他の候補者への対応が遅れる原因になります。連絡手段は電話でもメールでも構いませんが、迅速に伝えることが最優先です。
人材紹介経由で応募した場合は、担当者を通じて連絡するのが一般的ですが、直接応募の場合は自分で対応しましょう。誠意をもって対応することで、転職市場における自身の信用を守ることにつながります。
Q4. 30代・40代は何社くらい応募すべき?
30代・40代の転職では、平均して10社程度の応募が一般的です。なぜなら、書類選考や面接の通過率を考慮すると、一定数の応募が必要だからです。
例えば、30代前半の営業職で即戦力が求められる場合は、5社程度の応募でも内定を得られるケースがあります。
一方で、異業種への転職を目指す場合、選考通過率が下がるため、15社以上応募することが推奨されます。自身の経験や希望する業界の選考基準を考慮しながら、適切な応募数を決めることが大切です。
20代で転職する時に成功する6つのポイントを解説!良い転職のやり方とは
30代で転職成功に導く8つのポイント!転職のメリットデメリットや注意点も解説
40代での転職はやめた方が良い?難しい理由と成功させる6つのポイントを紹介
転職の平均応募数のまとめ

転職活動において、平均的な応募社数は約10社とされています。効率よく転職を進めるためには、複数の企業に応募し、同時進行で選考を進めることが重要です。
特に短期間で転職を成功させたい場合は、一度に複数社へ応募し、スケジュールを調整しながら面接を受けることで、スムーズに内定獲得へとつなげられます。しかし、ただ応募数を増やすだけではなく、選考対策にしっかり取り組むことも欠かせません。
履歴書や職務経歴書のブラッシュアップ、面接対策などを入念に行うことで、より良い結果につながるでしょう。
つまり、転職の成功には「平均10社」という応募数を目安にしつつ、自身の状況に合わせて応募戦略を練ることが大切です。